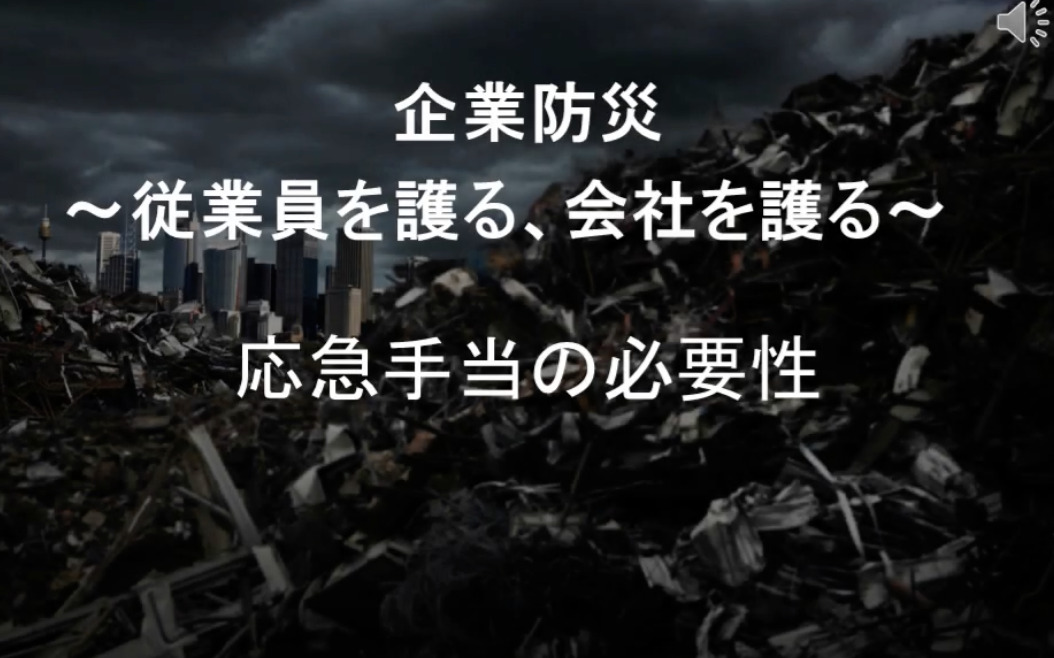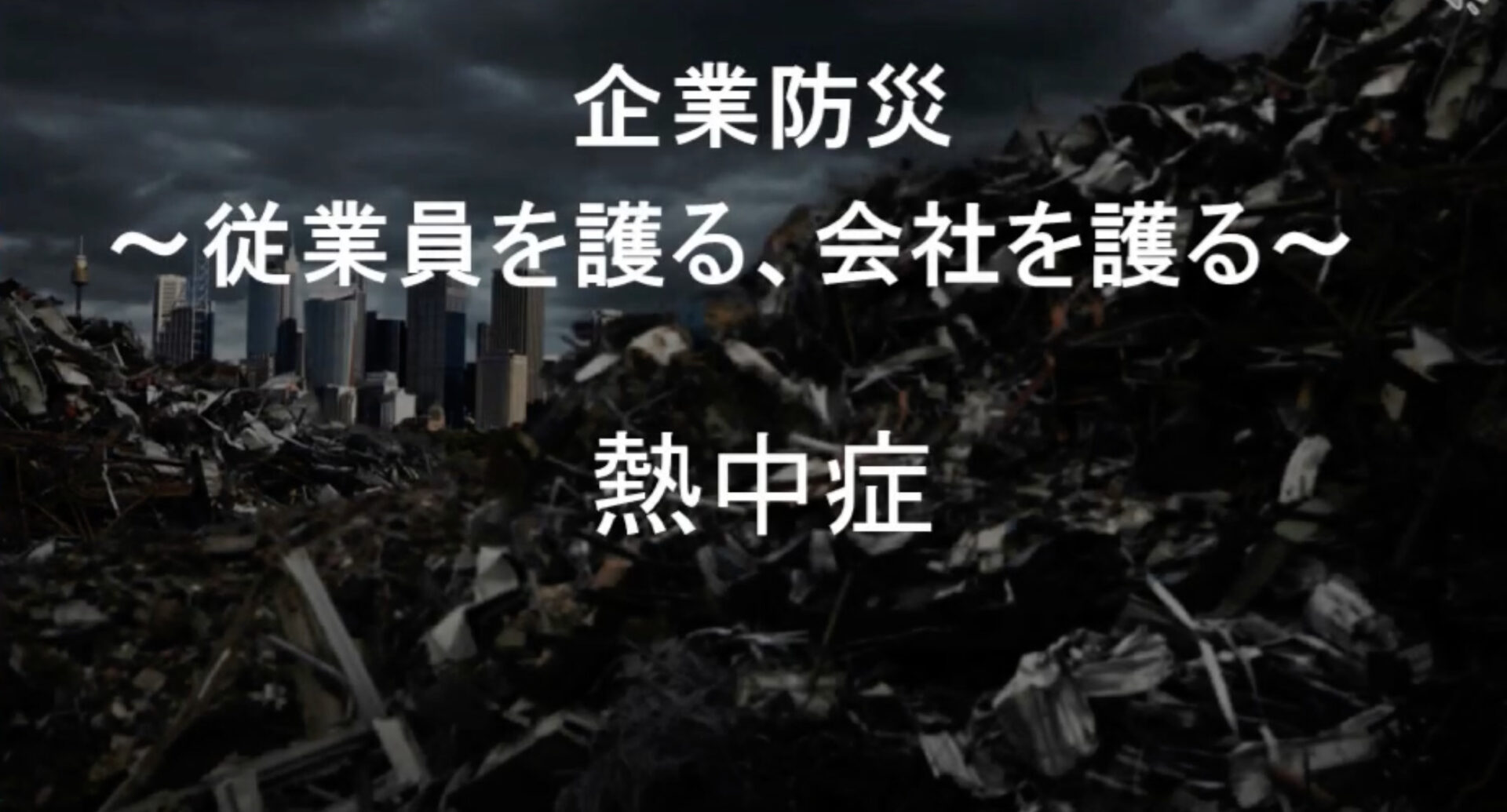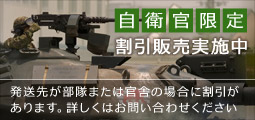↑動画は赤い再生ボタンをクリックしてください
今回はですね、えっと、共有してもらった
資料から戦場での応急処置、特に
止血帯の使用法についてちょっと
深く見ていきたいと思います。
ええ、止血帯ですね。極限状況での、
ま、命を救うための手順です。
はい。この資料からその正しい使い方、
あと、なぜそうするのかっていう
背景にある理由ですね。
そのエッセンスを掴んでいきましょう。
行きましょう。
まず、あの、最初にちょっと驚いたのが、
使う止血帯は負傷したその本人が
持ってるものを使うっていうのが
原則なんですね。
ああ、そうなんです。はい。
しかも、すぐ使えるようにあらかじめ
パッケージから出しとくと。
ええ。なんかもう一刻を争う現場の、
こう緊迫感みたいなものが
伝わってきますよね。
まさにもうスピードが本当に
生死を分ける場面ですから。
うん。うん。だからその準備の重要性と、
あとアクセスのしやすさ、それが
再優先されるわけです。
なるほど。なるほど。
で、次に大事なのが適用箇所ですね。
どこに巻くか。はい、適用箇所。
資料だと、まず四肢の負傷に用いるって
限定してます。手足ですね。
あ、手足だけなんですね。
胴体とかじゃなく。
ええ、そしてさらに重要なんですけど、
負傷箇所に関わらず、できるだけ
四肢の付け根に近い部分を縛ると。
えっと、負傷箇所に関わらずですか?
例えば腕の先の方の怪我でも。
そうなんです。腕の先でも足の先でも、
とにかく付け根に近いところ。
腕なら肩の近く、足なら股関節の近くです。
へえ。それは何か理由があるんですか?
これはですね、ま、混乱した状況でも
処置者が迷わず、かつ確実に
失血効果を得やすい血管を
圧迫できるポイントを選ぶという
意味合いがあります。
ああ、なるほど。ある意味こう
シンプル化して間違いを防ぐみたいな。
ええ、その通りです。ある種の安全策、
ルール化されているわけですね。
時間をなくすと。
確かに。
それで、えっと、締め付け具合については
どうですか?ここも重要で、
可能な限りきつく締めると。
可能な限りきつく。
はい。もう緩めは許されないという
くらいの意識で。
それでも完全に失血できない可能性もあって、
最近では、1本の腕とか足に
2本あるいは3本も使う例があるっていう。
そうなんですよ。ちょっと衝撃的でしたね。
ええ、それだけ、ま、出血をコントロールするのが
難しい、深刻なケースが多いってことですね。
うん。なるほど。
で、この締め付けに関連してもう1つ、
欠かせない手順がありまして。
はい。時刻の記録です。
時刻ですか?
ええ、止血帯自体に、ま、書き込める
ラベルがあればそこに、あと負傷者の服ですね。
服に。はい。油性のマジックで
Tという文字とあと時刻、
例えば「T10:25号」みたいに記入すると。
TはターニケットのTですね。
服っていうのはやっぱり後で医療従事者が
見つけやすいように。
まさに確実に情報を伝達するためですね。
ただ資料にもあるように、ま、汗とか
血液、泥なんかでうまく書けない場合もあると。
ああ、そうか。そこも現実的ですね。
ええ、でもこの時刻情報っていうのは、
後方の医療チームがいつから
その部位への血流が止まっているかを
知る上で本当にこう生命線になる
情報なんです。
処置の判断に関わるわけですね。
はい。だから書けない可能性も
ちゃんと記されていると。
そしてもう1つ、非常に重要な原則が。
何でしょう?
一旦縛ったら、決して緩めないということです。
緩めない?
はい。絶対に緩めない。
それはやっぱり下手に緩めると、またドバッと
出血するリスクがあるからっていうことですか?
ええ、まずそれが最大の理由ですね。
最出血のリスク。
それに加えて、長時間血流が止まっていた
組織から血流が再開する際に、
体にとって有害な物質が急に全身に
回ってしまうというリスクも指摘されています。
ああ、そういうこともあるんですね。
ですから、緩めるかどうかの判断、
あるいは外す判断というのは、
ちゃんとした医療設備が整った場所で
専門家が慎重に行うべきことなんです。
なるほど。現場の判断で勝手に
緩めちゃいけないと。
そういうことです。まさに鉄則ですね。
うーん。現場での応急処置とその先の、
ま、病院とかでの本格的な治療を
つなぐための大事なルールなんですね。
ええ、まさに。
今回の資料から、「できるだけ付け根に」
「可能な限りきつく」
「時刻を記録して」「そして緩めない」
っていう具体的なポイントが
はっきり見えてきましたね。
そうですね。
あの、特にこれは、本当に過酷だなと
感じた記述なんですけど、あまりの激痛で
負傷者本人が無意識にその止血帯を
外そうとしちゃうことがあると。
ああ。はい。
だから、可能であれば誰かそばについて、
それをさせないように見守る必要があるっていう。
ええ。なんかもう単なる処置の話だけじゃないんですね。
そうなんです。まさにその通りで、
これらの手順っていうのは決して
机上の空論ではなくてですね、
多くの厳しい経験、あるいは犠牲の上に
積み重ねられてきた、生存率を
本当に最大限に上げるための
知恵の結晶みたいなものなんです。
うん。
だから、止血帯に時刻を書くっていう
一見シンプルな行為1つにも、
そうした重みが込められているわけですね。
いや、本当にこういう極限状況での
判断基準とか手順を知ると、
いろいろと考えさせられますね。
ええ、これは重要な問いを提示しますね。
資料にもあるように、こういう極限の状態で
迷わず実行するために、ここまで最適化された
ルール作りというのは、もしかしたら普段の、
ま、平時に生きる我々の危機管理、
例えば自然災害への備えとか、
そういうものにも何か応用できる視点が
あるんかと。
なるほど。確かにそうかもしれないですね。
極限状況から生まれたある種の最善策を
私たちの日常のリスク管理に
どう活かせるか。
あなたもこの資料を読んで、
そんな視点を感じたかもしれませんね。
ええ、考えるヒントになりそうです。
はい。これはちょっと考えてみる価値が
ありそうですね。