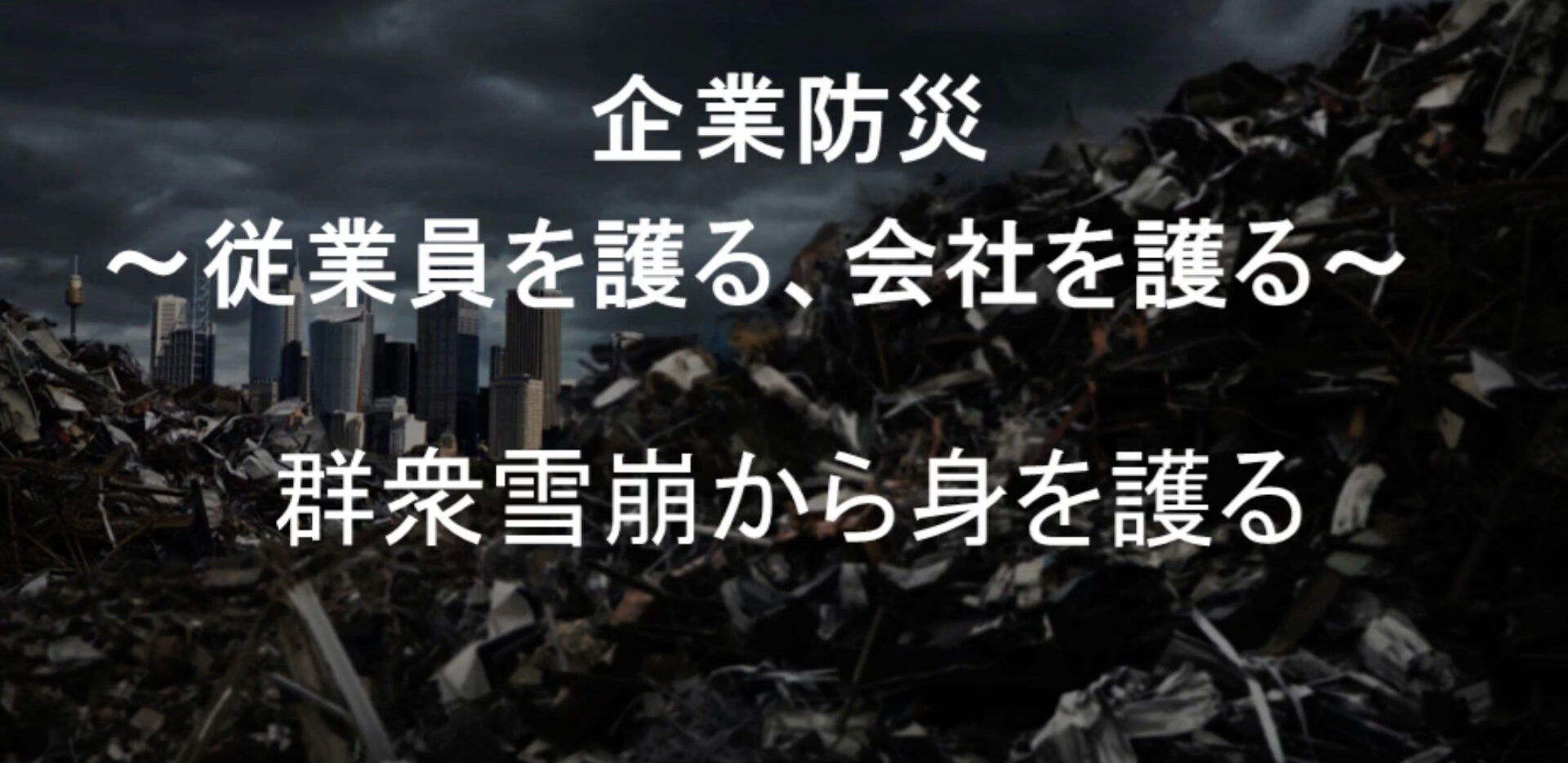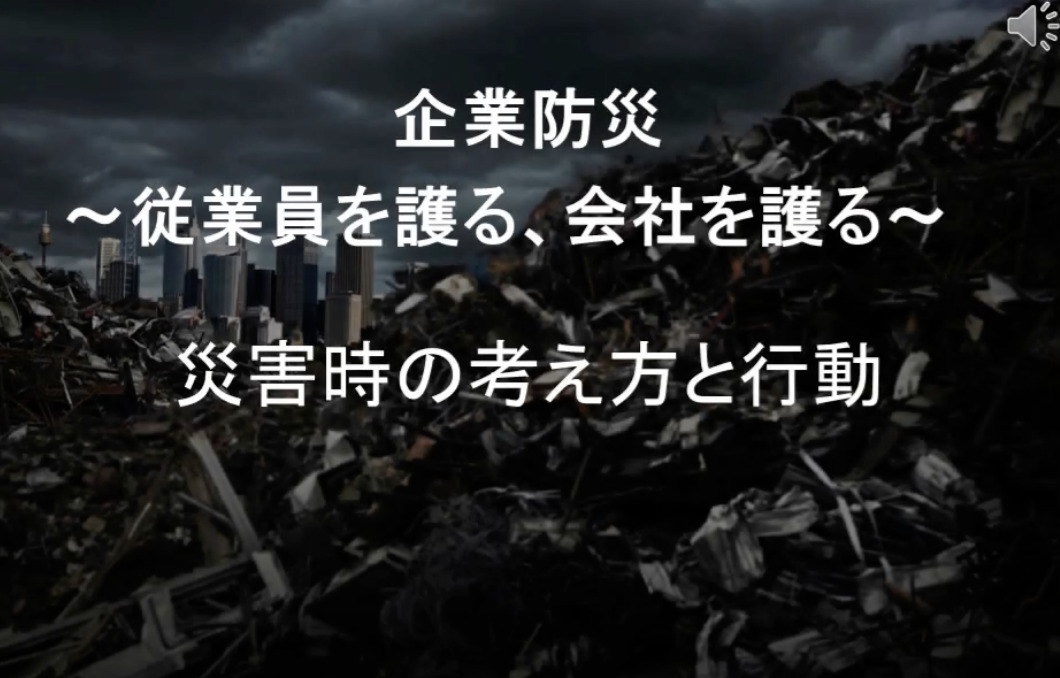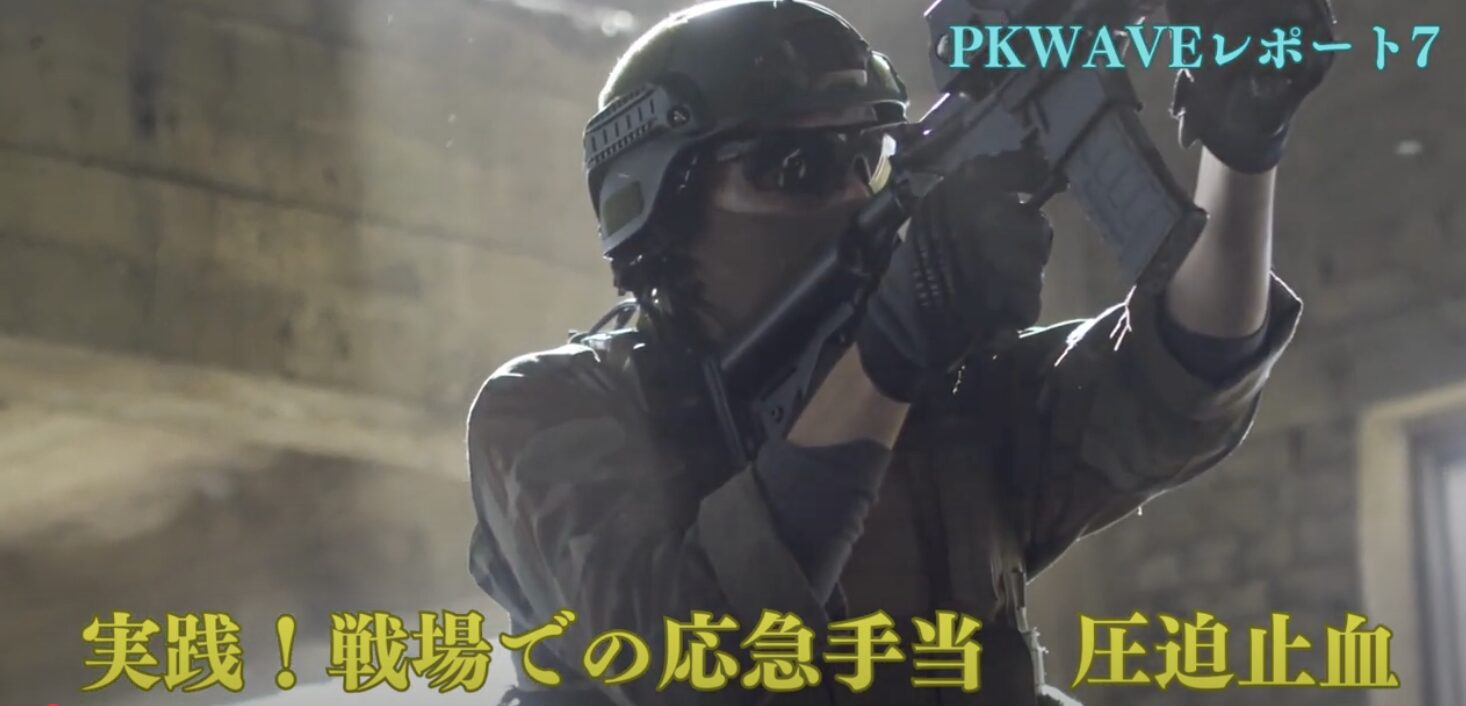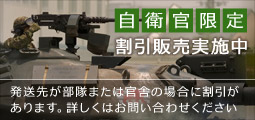↑動画は赤い再生ボタンをクリックしてください
さて、今回は戦場での応急処置という、
え、かなりシビアなテーマですね。
はい、そうですね。
お手元の資料にもありますけど、
止血帯とか本当に基本的な技術が、
生死を分ける、そういう世界の話です。
ええ、今回は特にその極限状況での、
行動原則、政府について資料を元に、
見ていきたいと思います。
政府原則SAFですね。はい。
脅威の無力化。ストップ・ザ・バーニング・プロセス。
現場状況の把握。アセス・ザ・シーン。
自身の安全最優先。フリー・オブ・デンジャー・フォー・ユー。
そして評価。EVAL・エト・フォー・ABC。
この頭文字です。
なるほど。この順番に意味があると。
まさにこの順番が非常に重要になってきます。
ではまず最初のS、ストップ・ザ、の無力化。
これは、ま、当然といえば当然かもしれませんが。
そうですね。攻撃が続いている状況、
例えば銃撃戦の最中とか、
あるいは爆発物がまだあるかもしれないとか。
ああ、なるほど。
そういう状況ではまずその脅威を取り除かないと、
救助に向かうこと自体が危険すぎます。
救助者自身が危ないと。
ええ、資料にもはっきり書かれていますが、
非武装の救助者は脅威がなくなるまで、
安全な場所に待機する。これが鉄則です。
自分が次の犠牲者になったら、
元も子もないですもんね。
その通りです。
で、脅威が去った、あるいは抑えられたと判断したら、
次がA、アセス・ザ・シーン。現場状況の把握。
はい。ここも重要で、
単に「もう大丈夫だろう」じゃなくて、
具体的に状況を確認します。
具体的にというと?
例えば敵がまだ存在している可能性はないかとか。
うん。うん。
他に未発見の罠、
例えば仕掛け爆弾とかそういうものはないか?
それから負傷者が何人いるのか、どこにいるのか。
ああ、人数と場所。
ええ、そしてパッと見で重症なのかどうか、
大まかに把握する。
この情報収集が次のステップ、
つまり負傷者に近づけるかどうかの判断につながります。
冷静さが求められますね、これも。
そうですね、非常に。
そして次がF、フリー・オブ・デンジャー・フォー・ユー。
自身の安全を最優先。
ええ。
資料には「安全でなければ見殺しにする」
とかなり直接的な言葉で書かれていますが、
これは感情的にはすごく抵抗がありそうです。
まさに本当にここがこの原則の、
ま、核心部分とも言えますね。
核心ですか?
ええ。助けたいっていう気持ちは当然強いんですが、
それで飛び込んで自分が負傷してしまったら、
もう誰も助けられない。
確かに。
本来助けられたかもしれない命も、
そして自分の命も失う可能性があるわけです。
うん。厳しいですね。
統計的に見ても、やはりこの原則を守る方が、
結果としてより多くの命を救えるとされています。
なるほど。
もちろん訓練された兵士であっても、
仲間を見捨てるかもしれないっていうこの判断には、
なんていうか本能的な抵抗を感じるものです。
でも二次的な被害を防ぐためには、
もう不可欠な判断なんです。
うん。本当に重い原則ですね。
感情と合理性のせめぎ合いというか。
ええ、そう言えるかもしれません。
その厳しい判断を経て、よし。
安全は確保されたと判断したら、
初めて負傷者の元へ向かうわけですね。
はい、そうです。
負傷者のところにたどり着いたら、まず何を?
まず、もし大量に出血していれば、
とにかく止血帯などを使って応急処置をします。
それから、負傷者が武器を持っている可能性もあるので、
それを安全な状態にする。
ああ、なるほど。武器の確保も。
ええ、ただこれも状況次第で、
例えばまだ危険が残っているような場所なら、
処置よりもまず安全な場所へ運び出すことを、
優先する場合もあります。
常にケースバイケースの判断が必要だと。
そういうことです。
そして安全な場所で、
あるいは安全を確保しながら、
最後のEVAL・リエト・フォー・ABC。症状の評価ですね。
はい。ここでABC。
つまりエアウェイ=気道確保、呼吸、そしてサーキュレーション。
資料ではブリーディング=出血と、
コンシャスネス=意識レベルも重視されていますね。
生命に直結する部分をチェックします。
ABC評価=気道・呼吸・循環・出血・意識レベル。
え、そう。もし負傷者が複数いる場合は、
このABC評価に基づいて、
誰から治療を始めるべきか、いわゆるトリアージを行います。
トリアージ=治療の優先順位付けですね。
はい。限られた時間と資源の中で、
最も助かる可能性が高い、
あるいは最も緊急性が高い重傷者から処置していくのが基本になります。
ということはこの政府原則っていうのは、
単なるステップの順番というだけじゃなくて、
ええ。
極限状況下で最も多くの命を救うための、
なんていうかすごく合理的な思考プロセス、
思考の枠組そのものということなんですね。
まさにそう言えると思います。
脅威をまず止めてS。状況をしっかり見てA。
自分の安全を何よりも確保してF。
その上で初めて評価と処置に移ると。
ええ、特にあのFの原則。
「安全でなければ動かない」というのは、
感情的には非常に難しいですが、
究極的には合理的な判断に基づいているわけです。
そして複数の負傷者がいた場合のトリアージも、
これもまた厳しい選択ですけど、
全体の生存率を最大化するためには、必要な判断だと。
はい。そういうことになりますね。
うん。今回この資料を通して、
極限状態での意思決定のプロセスに触れてきましたけど、
リスナーの皆さんにとっては、
こういうプレッシャーの中で手順を守ることの大切さとか、
あるいはその自分の安全を確保することの価値について、
どう感じられるでしょうかね。
そうですね。
そして最後に、ちょっと視点を広げて考えてみるのも、
面白いかもしれません。
と言いますと?
今回の資料は、あくまで現場での、
本当に最初の数分間の対応に、
焦点が当たっていましたよね。
ええ、初期対応ですね。
ではこの初期対応、初期安定化の後。
搬送された先では一体どんな医療が待ってるのか。
そしてこの最初の数分間の行動判断が、
その後の長い治療のプロセスとか回復に、
どういうふうに影響していくのか。
ああ、なるほど。その先まで考えてみると。
ええ。そこに思いを馳せてみることも、
また深い学びがあるんじゃないかなと、そう思います。